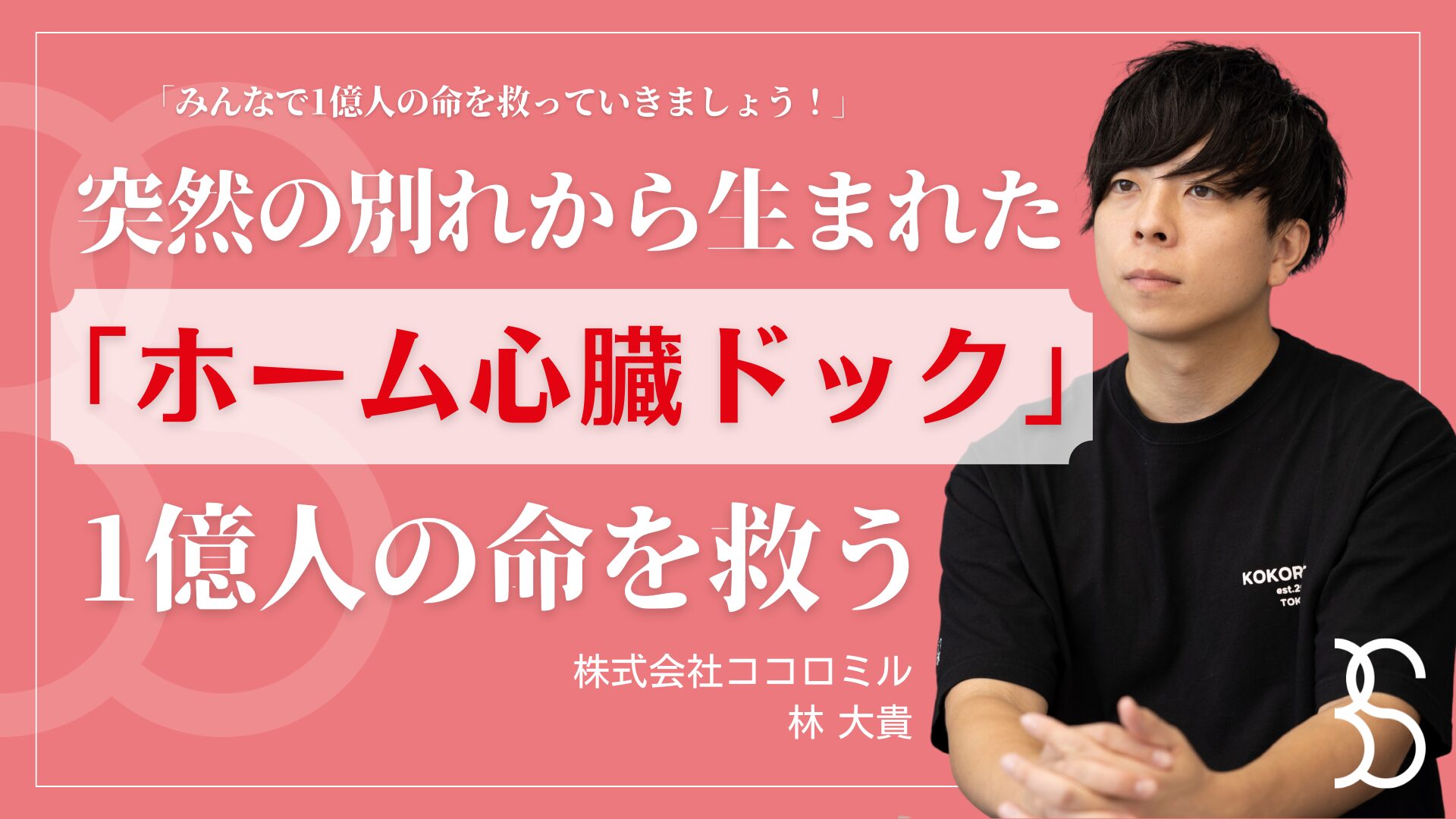
株式会社ココロミル 林 大貴
今回は、ヘルスケア領域の事業で活躍をされている林様のビズストーリーをお届けします。
- こんな方におすすめ
-
・ヘルスケア事業に興味のある方
・従業員との関わり方
・自分の原体験をもとに事業を考えたい方
- こんなことが学べる
-
・社員や顧客との関わり方
・相手の課題の見つけ方
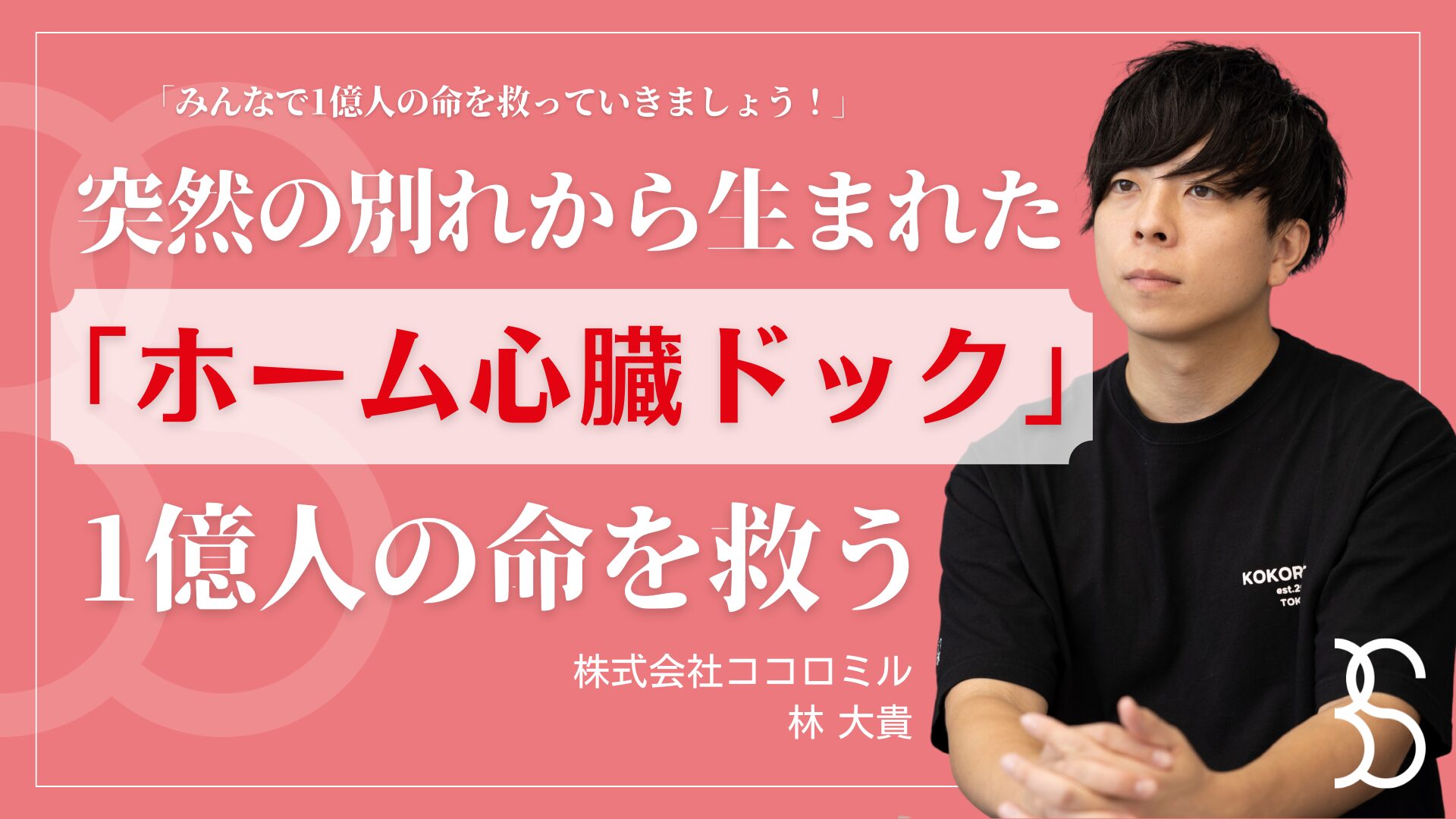
株式会社ココロミル 林 大貴
今回は、ヘルスケア領域の事業で活躍をされている林様のビズストーリーをお届けします。

弊社は「ホーム心臓ドック®︎」という、自宅で受ける心臓ドックというものを提供しております。立ち上げた背景として日本では「今、6分に1人が心臓病で突然死をしている」というような中で、健康診断や人間ドックを受けているから私は大丈夫という方がたくさんいらっしゃるんですけれども、そういった方々に早期発見や気づきの場を設けることで皆さんの健康寿命を伸ばしていくというようなところのサービスを展開しております。
-ありがとうございます。確かに「急に死ぬかもしれない」という可能性って誰もが絶対ありますよね。そうなった時どうしようっていう意識を持たれている方って、特に貴社のお客様になる方だと経営者が多いのかな?と思うのですが、どういった方がメインのお客になるのでしょうか?
そうですね。弊社の売上の7割が福利厚生として導入いただくことが多いんです。あとの3割が個人なんですけど、個人の方の購入でいくとやっぱり経営者の方は結構多いですね。というのも、社長は自分に課されている責任が大きいからこそだと思います。
例えばココロミルで言ったら僕ですけど、何かあった時にココロミルで働いている社員及びその先の家族全員に迷惑が及ぶので、社長の皆さんは健康に対しての意識はかなり高いです。
なので、ご自身の健康状態チェックで活用いただくことはすごく多いです。
-そうなってくると、福利厚生で導入されている企業様が多いのは、社長が個人で使ってみて、導入してみよう!ということが多いのでしょうか?
そのパターンが大半なんです。なので導入企業様に貸し出しをして、皆さんに日々の健康維持のために使っていただいています。
-社長自ら意識されて福利厚生として社内メンバーの健康を気遣っているのも素敵ですね!ちなみに人間用だけではなく、動物向けにもサービス展開されていると思ったのですがこちらはどういった背景で事業をされているのでしょうか?
動物の方は現在は獣医師さん向けになってまして、動物病院で受けていただく検査になっています。動物病院でも心臓病特化型の先生は全体でも数%と言われているくらいなんです。ワンちゃんでいうと、チワワやトイプードルなどの小型犬の死因の1位は心臓病と言われています。全体の数%しかいない中、正しい診察ができるまでに時間がかかってしまいワンちゃんがなくなってしまうこともあるので、人間だけでなく動物の課題も解決できるような取り組みをしています。
-では最初から動物用にも使えるようにしよう!と思って始めたわけじゃないんですね!どのタイミングでこの事業をやろう思ったのでしょうか?
ありがとうございます。いくつかあるんですけど、1番は僕が飼っているフェレットが急に体調を悪そうにしていたので、病院に連れていったら膀胱破裂していたんです。膀胱破裂って、人間だったら失神して多分死んでると思うんですけど……言葉を話せない動物たちっていうのは、それに耐えて飼い主に気づいてもらってやっと治せるっていうような状況なんですよね。それを少しでも早期発見できるとか、動物が今抱えている病気に気づけるようにできたら良いなと思って、「今は人間に使ってますがペットにも使えませんか?」と言ったことが始まりです。
起業した背景の1番の理由は、僕とご飯食べた12時間後に母親が急に倒れてしまったからです。一緒にお酒を飲んで、ごはんを食べた12時間後に血を吐いて倒れていたんです、信じられますか?何が起きたかわからなかったです。それから大学病院に運ばれましたが、最終的に脳出血という病気だとわかって脳を切り開いて手術もしてもらいましたが、59歳という若さで亡くなりました。当時、お医者さんから「脳の血管年齢が80代だよ。お母さんってすごくストレスを感じてませんでしたか?」って言われたんですよね。
うち5人家族なんですけど、確かに母親とちゃんと話せるのって僕しかいなくて「ストレスは感じてたと思いますけど、なんでですか?」っていう話をしたら、「これは慢性的にストレスがかかってないとこんな結果にはならないよ」と言われたんです。「じゃあ先生、ストレスってなんですか?」って話をしたら、「よくわかんないんだよね」って言われて……「じゃ、僕の母親はよくわかんないものに命奪われたんですか?」「いや、そう言わざるを得ないかな」って言われて、それがもう全然納得いかなくて。
だからこそストレスって一体どんなものか調べ始めたら、ストレスから1番ダメージを受けるのが心臓だということがわかりまして、ホーム心臓ドックといったところに目をかけてスタートしました。
-ありがとうございます。林さんのご経験あってこそだとは思いますが、ストレスで実年齢と脳の血管年齢ってそこまで変わってしまうことに驚きです…!
出ますね。テレビとかだとストレスを感じている人とそうでない人で肌年齢が変わるっていうじゃないですか。それと一緒で身体のいろんなところに影響が出ます。
-なるほど…ちなみにお母様は持病はお持ちじゃなかったのでしょうか?
持ってなかったんです。それこそ健康診断や人間ドックは毎年受けてましたし、何か変なものが見つかるっていうのは特になかったなっていう感じでした。
-となってくると本当に人間の身体はいつどうなるかわからない状況にあるからこそ、ホーム心臓ドックで定期的に診断していかないとならないですね。
そうですね。本当にうちのサービスは1年に1回とかでも全然いいんですけど、やっておいた方が良いです!

–ここまで事業を伸ばしてこられた要因ってどこにありますか?
医師の信頼性を得たっていうのが1番大きなポイントです。うちで使ってる自宅で受ける「ホーム心臓ドック®︎」の機械は、日本にある大学病院の82棟のうち23棟で使用されているものになっています。なので、医師たちがしっかりと認めているものになっています。
一方で、他社さんのヘルスケアのサービスに目を向けると、どうしても精度というとこには疑問が残ってしまいがちです。例えば、尿からガン検査やりますとか、頭髪からストレス検査ができるようになるとか……ただ結果を見ると、占いみたいなものになってしまっているんです。自分たちの中で解析した結果「〇〇だと思います」みたいなのが出てくるんですけど、擬陽性もすごく多い。
僕たちの製品はそもそも心電図と言われる、どこでどんな異常があったかっていうのを見てすぐにわかるものになっているので、擬陽性がほとんどないものになってきます。その結果、お医者さんたちはそれを見た時に「この人はこういう病気だよ」ってすぐに言えます。なので、お医者さんたちの信頼を得た、またお医者さんたちがそもそも使っている機器を使っているといったところで、他のヘルスケア企業よりは割と伸びているのかなと思ってます。
-ありがとうございます。ちなみに大学病院にはどのような感じで導入が進んでいったのでしょうか?
僕たちは現場の声を重視したんです。いろんなお医者さんにヒアリングをして、どんなものがあったら患者さんが喜ぶか、そして医療の現場の人たちの負担が減るか、ここにフォーカスをしていきましたね。
僕が特に重視したのは後者の方で、病院で働いてる人って、残業が多かったりもしますし、現場の負担をどうやったら減らせるかにはかなり注力したポイントだったので、そこも喜んでいただけたのもあって導入が進んでいきました。
-これから事業を伸ばしていくにあたって課題になりそうなポイントはありますか?
大きく分けて2つあります。1つ目が心臓病に対する啓蒙活動だと思っています。ここはすごく想像しやすいと思うんですけど、大田原さんは「癌」って怖いですか?
-ガンは怖いですね。
そうですよね、心臓病って怖いですか?
-……と言われると、心臓病がなんなのかがわかってないです。
そうですよね。本当にそこに課題があると思っていて。
例えば医療ドラマを見ていても、癌だと抗がん剤をして髪が抜け落ちて痛いと言ってるのを皆さんは想像すると思うんですよ。なので、「癌にはなりたくないな」と無意識に思っていると思います。ただ、心臓病って基本的に突然死したりとか、その後寝たきりになったりとかしてくるので、心臓病に対する想像が皆さんつかないんですよね。
実際に癌で苦しんでる姿っていうのは皆さん見ているので、想像がつくからなりたくないってなるんですけど、心臓病に対しては皆さん想像がついてないので、僕は「いや、心臓病って本当は突然死するんだよ」とか、そうでなくても、その後寝たきりになって家族に迷惑かけちゃうんだよみたいなところを皆さんに伝えていかなきゃいけないなと思ってます。僕たちが先陣を切って「本当は心臓病は怖いです」っていう活動をしなきゃいけないなと思ってます。
2つ目が、国民皆保険という制度です。もちろん素晴らしい制度ですが、人の意識として「病気になったら病院に行けばいい」というもの意識がすごく強いんです。でも、アメリカとかなら病院行ったら1回で10万円や20万円費用が掛かるので、そもそも皆さん早期発見をしようとするんですけど、日本はそれがないっていったところが大きくて。
もっと厄介なのが、心臓病って自覚症状がほとんどないんです。ちょっと動悸がする、息切れがするくらいなんですなんですよ。大田原さんは動悸がする、息切れがするって感じた場合ってどうしますか?
-ちょっと休もうかなって感じですね
そうなんですよ。なのでそこがすごく難しくて、ちょっと頭痛がする時や熱が出たら、それは病気かもしれないですけど、動悸がするって言って病院にいく人はほとんどいないです。そうすると心臓病が見つかった時には、心筋梗塞で急に倒れたり、突然死してしまう確率が上がってしまいます。なので、啓蒙活動とこの国民皆保険で、日本国民のヘルスケアリテラシーをあげなきゃいけないなって思ってます。
-確かに健康に関して興味がある人がいてもリテラシーの情報格差はありそうですね。何か他に伝えていることはありますか?
いつも伝えていることがあるのですが、「心臓マッサージ」ってあるじゃないですか。
命に関わる場面で、他の臓器マッサージしてるの見たことありますか?例えば「肝臓マッサージ」は多分聞いたことないと思います。癌であろうと、事故で骨が折れても、最終的に命がかかった医療のドラマシーンで見るのって、「戻ってこい!」って言いながら心臓マッサージしてるじゃないですか。結局、心臓が元気じゃないと人って死んでしまうので、そもそも心臓を元気にするっていった意味でいくと、心臓の状況っていうのを毎年読み取るっていうのは必要です!
–林さんが経営をする上でこだわっていることはなんでしょうか?
2つ目線があります。まず1つ目が「社員目線」でこの会社で働きたいって社員が思う会社にすることと、最終的に振り返った時にこの会社で働いて良かったと思えるような会社にすることにはこだわっています。
いわゆる出来たてのベンチャーって、社員の評価制度を作る余裕もないし、おそらく福利厚生を充実させようっていう余裕もないと思うんですけど、僕はそこから取り掛かりました。あとは、社員から出てくる提案はあんまり否定しません。とりあえずやってみて、失敗してから学べばいいじゃん!って思ってます、失敗しても、謝るのが社長の仕事ですからね。
2つ目は「お客様に対しての目線」です。「こんなサービスあったらいいよね」っていったところを僕たちは必ず生み出していくっていうのを意識しています。なのでお客様からのクレームは、ほとんどないですね。
むしろお客さんから「本当にこのサービス使って良かったです」とか、お手紙が届いたりします。これもお客様に寄り添って来たからだと思います。
起業当初に向けた、自分へのアドバイスはないですね(笑)全部が良い経験だったと思っています。なので、これから起業する方へのアドバイスをするのであれば考えすぎないことですかね。行動する前に考えろっていう人もいますし、考えすぎないで行動しろっていう人もいると思うんですけど、どっちつかずになってもダメで、考えながら行動しなよ!と僕はよく言ってます。
考えすぎる人は結局慎重になってしまっているだけで、行動してみたときに考えてたことって全然問題じゃなかったじゃんって気づくし、考えなさすぎて行動する人は何も考えてないなって「意思」がないので相手にされなくなるので、考えながらちゃんと行動していくっていうのが大事だと思います。
また、知的好奇心を持ってないとダメだなと思ってます。
例えば、僕だったら役員と高速道路を運転してて、「なんでここにこんな看板があるんでしょう?」みたいなことを問いかけるんですけど、「林さんといると疲れる」って言われたことがあります。それくらい日常から「なぜ?」と考えることが多いです。
社長って自分たちの後ろにいろんな人の人生を背負っているので、自分が考えすぎるぐらい考えないと社長ってなれないと思いますし、自己犠牲のメンタルがないと社長にならない方が良いと思っています。

一緒に働いてくれてありがとう!ただそこだけですね。仕事ってこの世の中に数万、数百万あって、いろんな会社がたくさんあったり、いろんな働き方がある中で、うちはリモートは基本的に週1までだよとかって言っていて、時代に逆行する会社だと思ってます。人生の大体3分の1がお仕事に時間を費やしていく中で、今で言ったら寿命は80歳ぐらいですかね。その中の時間で仕事をする3分の1ぐらいの時間をこの会社に使ってくれて改めてありがとう!
ココロミルとして、みんなで掲げてる夢が1つあります。それは「世界で1億人の生命を救うこと」になっています。なので1億人の命を救うまでは、僕はあと10年でも20年でもこの会社で駆け抜けていこうと思っているので、それを達成したいです。
▼世界初の自宅できる心臓ドック
 株式会社ココロミル
株式会社ココロミル 